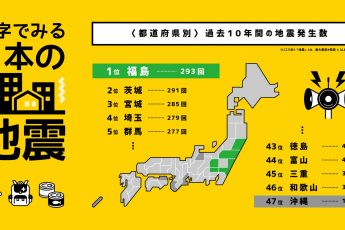東日本大震災に伴う原発事故のため、全域が避難区域となった福島県南相馬市小高区では、すべての住人が地域外へと避難。再び居住が可能になったのは5年後の2016年だった。
一度人口がゼロになった地域からは、生活に必要な店も医療機関もコミュニティも消失。小高生まれの和田智行さんは、地域の人々が再び地域で暮らすベースを作るために、居住可能になる前から人々が集まれるコワーキングスペース〈小高ワーカーズベース〉、食堂、商店と必要な事業を次々と立ち上げ、さらに地域で人々が柔軟に働いて暮らせるよう、ハンドメイドガラス事業を展開。
「地域の100の課題から100のビジネスを創出する」をミッションに掲げ、現在は株式会社として事業展開を続ける〈小高ワーカーズベース〉のありようから、パンデミックや災害のような大きな変化を経てなお、しなやかに持続していける地域、ビジネス、人のあり方を教えていただいた。

地域に再び住める日が見えないなか、立ち上げた事業
小高で生まれ育った和田さんは大学進学と同時に上京し、卒業後はIT企業勤務を経て仲間とともにITベンチャーを起業。10年間東京で暮らした後、2005年に実家を継ぐため地元・小高へUターンした。リモートワークでIT企業2社の役員として働き続けていた最中、震災に遭い、地域外での避難生活を余儀なくされたという。翌年の2012年には創業から携わっていた2社を辞め、会津若松の企業で働きながら創業支援の研修を受ける生活を始めた。いずれ小高に戻って生活できるようにとビジネスを模索していた和田さん。当時、小高を視察、訪問する人々を案内する機会が多かったが、そこで何も生まれないことに疑問を感じたという。
「宮城や岩手は同じようにいろんな人が来て、地元の人と協業してプロジェクトが生まれていたのに、小高では何も生まれていかない。なぜかと考えたら、皆さん現場を見てすごいショックを受けて、何とかしなきゃいけないとか、会社に掛け合って何か支援できるように動きますとか言ってくださるんですが、その熱が高まったときに現場で地元の住民と何か具体的なアクションを起こし始められる環境がないからなんじゃないかなと思いました」
この思いから和田さんは、立ち入りが可能になった小高でコワーキングスペースを立ち上げることを思い付く。東京でもコワーキングスペースが流行り始めていた。まだ小高に住むことはできなくても、コワーキングスペースがあったら、フットワークの軽いクリエイターやフリーランサーたちが集まって、何かプロジェクトが始まるのでは、と考えた。いつ小高に居住が再開できるかの見通しも立っておらず、地面には船や車が転がったままの状況。ここが「小高ワーカーズベース」ひとつめの事業のはじまりだった。

「周囲からは、コワーキングスペースは人がいる場所につくるものだ、と散々言われましたが、それ自体を収益化しようとは思っていなくて、まずは僕らも身を置ける、かつ外の人が立ち寄れて、現場の課題が見えてくる場所にしたかったんです。そこから生まれてくる事業でしっかり収益を上げればいいと考えました」

その後は当時、地域に復旧工事や除染作業で日に5,000人ほどの作業員が訪れるものの、昼食を提供できる場所がなかったことから、食堂「おだかのひるごはん」をオープン。作業員の方が寒空の下で弁当を食べているのを見て、温かい食事を提供したいと考えたのは小高が地元の60代のお母さんたちだった。近隣の避難先から小高に通い、日替わり定食を提供し続けた。(現在は終了)

また避難解除され、再び居住が可能になった2016年には、ものづくりの事業として、耐熱ガラスメーカーのハリオとの協働でハンドメイドガラスアクセサリーブランド「irise-イリゼ-」をスタート。
「いろいろ生活環境が整っても、地元の人たちの考えとしては、若い人はもうどうせ帰ってこないと諦めてしまっていたんです。そんな中で、若い人たちがやってみたいと思える仕事とか、子育てや介護があって外で働きにくいお母さんたちが働きやすい環境があれば、住むのは無理でも働きに戻って来るぐらいはできるんじゃないかと考えました」

決まった数を納品できれば働く時間は問わない。バーナーを引けば自宅でも仕事ができる。それに、かわいいものや素敵なものをつくって稼げる。そんな魅力が、若い人が地域に戻ってくる呼水になり、今では地元の人だけでなく地域外から移住してきた人も。さらに移住者が地元の人と結婚して子どもが生まれ、ここに暮らす仲間が増えていく。子ども園ができるなど、地域の子育て環境も整ってきている。

先行き不透明な時代をしなやかに進む姿勢
新しい事業を立ち上げる一方で、食堂や仮設スーパーはそれに代わる新しいものができて、役目を終えたため潔く終了。このしなやかなあり方が小高ワーカーズベースの基礎に流れている。

「僕らが震災を経験して強烈に感じているのは、未来は予測不能、いつ何が起きるかわからないということです。災害やパンデミックといった予期せぬことで事業が倒れてしまう可能性もある。だけどそれをネガティブに捉えるんじゃなくて、予測できない可能性もたくさん埋まっていると考えてみる。事業で言えば、一つの事業を長く続けることは大事ですが、一つの事業を大きくしていくことを目的にすると、本来は必要のないニーズをつくったり、売るために無理なプロモーションをしたりといった持続的でない部分が出てくる。そうではなく可能性をすくい取る、小さくても複数のプロジェクトを考える方が課題に沿えるし倒れにくい。僕らが地域の100の課題から100のビジネスを創出すると言っているのは、1000人を雇用する一つの事業、あるいは一つの企業に依存する街ではなく、10人雇用する100の事業があれば、その方が持続的だと思うからなんです」
和田さんは元々webの仕事をしていたこともあり、プロジェクトを早いスピードで立ち上げ、うまくいかなければスッパリと畳み、育てるべきものを育てるという姿勢が身に付いている。
「社会や環境の変化に応じて事業を立ち上げていく力や考え方を地域全体が持つようになれば、災害が起きようが何が起きようが街が機能停止することはないと思う。僕らは100の事業をつくることで、そういう風土を醸成することを目指しているんです」
なお終了したプロジェクトに関わっていたスタッフは、希望に沿って新しいプロジェクトに入ってもらったり、別のところに行きたければそれをサポートする。今でこそ一般的になった、回復する力=レジリエンスを体現する和田さんのあり方には、震災で直面した地方と中央の関係も影響している。
「僕たちは原発事故によって避難を強制されたという前提があります。原発が止まって困っているのは、そのエネルギーを使っている人ではなく、原発の周辺で暮らしている人たちなんですよね。住めなくなることだけではなく、仕事がなくなったり、経済が停滞してしまったり……。大きな産業に依存して暮らすことの構造的な欠陥に直面したわけです。地方が、中央の大きな資本や政策なしでは生きていけないというこの構図を壊したいと強く思ったときに、レジリエンス的な考え方に至ったという感じです」
個人に置き換えても、自分の仕事がいつ不要になるかもわからない先行き不透明な時代だ。
「それに対して恐怖を感じたり不安を感じたりして暮らすんではなくって、なくなったらまた作ればいいというふうにみんなが思えたら、すごいハッピーな世の中なんじゃないかなと思うんです。そのためには、勤め先や家庭といった世界だけで生きていくより、他の興味のあるコミュニティに出て、主体的に活動する。それが第3、第4以上の居場所や役割を持つことにつながりますよね」

小高に仮設のスーパーをつくったときには、地元の人に涙を流して感謝を伝えられたこともあった。だが地域のため、と意気込むより「基本は自分が作りたい世界を作るためにやっていて、そのフィールドが地元なんです」と軽やかに話す。自分のよろこびと周囲のよろこびが交わるところでなければ、たのしくないし続かない。このことも持続可能なライフスタイルのために見逃せない項目ではないだろうか。
この記事を書いた人

- 広告会社勤務後、フリーライター。生まれ育った東京から高知、さらに鹿児島へと移住。コラムやインタビュー記事を中心に執筆。インタビュアーとしても活動。